第一章 邪馬台国と古代中国
3世紀の中国で書かれた「魏志倭人伝」に邪馬台国への道順が書かれている。朝鮮半島の帯方郡から始まり対馬、壱岐、末盧国、伊都国までは明確であるが、その後の道のりは九州であるが、そのまま進むと九州をはみだし海になる事もあり、文の一部を読み替え、近畿・山陰等が邪馬台国の場所と考えられて決定していない。この議論は江戸時代からある。新井白石が魏志倭人伝を読みこなそうとした事、明治時代の東大対京大の戦いである。様々な説があるが、有力な説は九州説(代表的遺跡:佐賀県の吉野ヶ里遺跡)と近畿説(奈良の纏向〈まきむく〉遺跡)である。魏志倭人伝以前の文章である一世紀の「漢書」には倭人社会は100あまりに分かれ楽浪郡に定期的な朝貢をいていた事が書かれている。また、「後漢書」には紀元57年に倭の奴国の王の使者が洛陽で光武帝から金印を授けられた事が記載されている。
考古学では発掘した土器や木材が、いつの物であるかを特定する事は大変重要である。その手法として、土器編年表・放射線炭素年代測定・年輪年代法・酸素同位体年輪代法がある。
九州説の特徴は中国との絆の深さである。九州佐賀は朝鮮半島と地理的に近く交流が容易である。遺跡からも中国の古城との類似性を見る事ができている。
近畿説(纏向遺跡)では巨大な建物群があり、144畳にも及ぶ大きな建物があり、この建物を中心に東西に一直線に並ぶ建物の存在である。また、神技に用いる桃の種、建屋の木材が卑弥呼が中国皇帝から親魏倭王の称号を受けた239年とほぼ同時期の231年である事の判明である。
第2章 最新研究で迫る邪馬台国連合
魏志倭人伝では倭の国では30余の国からなるある。魏志倭人伝の中で更に、女王卑弥呼の邪馬台国と一大卒という諸国を検察する役割を持つ伊都国が記載されており他の国との差を示している。
これらを踏まえ邪馬台国の場所を推定すると以下の箇所がの挙げられる。
1.平塚川添遺跡(福岡県朝倉市) ※吉野ヶ里遺跡を含めた九州北部一帯のネットワークの中心
堀立柱建物跡150棟、竪穴住居約300軒という大規模な集落。監視集落を周辺に配置している。
2.纏向遺跡 (奈良県桜井市)
九州から関東に至るまでの広範囲な場所からの土器の出土がある。
3.出雲地方
ヤマタノオロチ伝説、「因幡のの白兎」で有名なオオクニヌシノミコトが住んだとされる土地である。
4.伊都国(福岡県糸島市)
平原王墓で発掘された40枚もの鏡。
5.吉備 楯築遺跡(岡山県倉敷市)
約80メートルもの双方中円形墳丘墓と特殊土器が発掘された。
何故、連合をする必要があつたのか?後漢書では倭国大乱が長く続いたとされ、その原因が127年の飢饉ではないか?と考えられている。これにより戦いが激しく行われたと推定している。この戦いが続く中、連合を作る事が提案され全体としてのコンセンサスになっていったと考えられて、卑弥呼が女王とする邪馬台国連合が形成された。主導権を握ったのはどの国か?
1.伊都国(九州北部)
魏志倭人伝では、伊都国に一大卒という諸国を検察する官職があったと記載されている。王墓からの豪華な装飾品も圧倒的な権力を示している。
2.唐古・鍵遺跡(奈良盆地中央)<からこかぎ>
最大の鋳型鋳造品である銅鐸が発見された。
3.特定の国なし
(伊都国と岡山吉備の連合)
魏志倭人伝での伊都国が漢王朝の崩壊とともに勢力を失った。
吉備では2世紀の墓では全国最大級の前方後円墳である。
この2つの勢力が、争い連合を作り卑弥呼を女王に祭り上げた。
この卑弥呼女王形体で、混乱が収まったと考えられる。
第3章「倭国大乱」と漢王朝の崩壊
後漢王朝が弱体化し始め黄巾の乱が184年に起こっている。この中国での混乱は日本にも大きな影響を与えた。中国からの難民が日本に来たと推定される。この事実を示す物として、鳥取県鳥取市青山町にある青谷上寺地遺跡である。ここからは農耕具や船の部品材料と共に110体もの人骨が見つかった。この人骨をDNA鑑定すると中国人と縄文人の混結を示す人骨が32人中31人であった。また、これら人骨は武器で傷つけられた物も多く治療される事もなく即死であったと推定される。これらの事実から、この遺跡では後漢崩壊に伴い中国から難を逃れた人々が奴隷として連れられて戦いの中で亡くなった可能性が考えられる。中国の混乱が日本の弥生末期の日本社会に大きな影響を与えたと考えられる。邪馬台国はこの様な中国との関係と倭国内での戦いの相手である狗奴国との関係上、邪馬台国連合を作り対抗したのではないか?と考えられる。魏志倭人伝には邪馬台国の南に位置する狗奴国と書かれているが、15世紀の李氏朝鮮の時代の地図でさえ正確に現在の地図ではなく、日本列島は小さく南に長い形と考えられていた。この事を考えると狗奴国は東海、関東に存在していたとも考える事ができ、邪馬台国とは文化的に受け入れ難い人達と思う事ができる。
第4章 卑弥呼×三国志 知られざるグローバル戦略
卑弥呼が魏に使者を送ったとされる238年頃は、中国・倭国共に政治的に複雑な状況にあった。
後漢が崩壊して魏蜀呉の三国時代にあって魏は2代目皇帝の曹叡がなくなり、幼帝が即位し後見人の司馬懿に権力が移行する様な時であった。倭国では卑弥呼の邪馬台国と狗奴国が交戦状態であり各々が戦略的提携を模索していた。魏は蜀を背後から攻撃する為に蜀の背後に位置するインドのクシャーナ王朝に親魏大月氏王というして金印を与えている。卑弥呼が金印を貰う10年程前の出来事てある。赤壁の戦いで呉・蜀に敗れた魏は様々な国との軍事的協力を計画していて、その一貫として卑弥呼への金印を贈った訳である。卑弥呼率いる邪馬台国は狗奴国との戦いの中で中国の後ろ盾を期待した。また、遼東半島にはこの時期、公孫氏正権が50年程続いていた。公孫氏は呉との関係であるが、呉は公孫氏を燕王とし魏と挟み討ちする計略を作った。しかし、これを察知した魏は公孫氏を滅ぼした。この様な背景の中での卑弥呼による魏呉のとグローバル戦略がなされたのである。しかし、邪馬台国の卑弥呼は狗奴国と戦っている最中にの247年頃、死亡するのである。
第5章 卑弥呼の最期と歴史の断絶
箸墓古墳(はしはこ)は、纏向(まきむく)遺跡南部の位置する全長280メートルの大きく左右対称の幾何学的な前方後円墳である。この大きさを長い年月維持しようと考えると基礎部分は高いレベルの技術が求められる。中国の王朝では広大な都にもこの様な技術があり「盛土」と言われている。魏の洛陽城もこの盛土が使われていたと推定する。
箸墓古墳は年代を調査すると、240〜260年の間に作られたと算出された。これは卑弥呼が死んだ日々と同一である。
魏志倭人伝では卑弥呼の死後、男性の王がたったが、国内の混乱は収まらず13歳の壱与が王となり混乱は収まったとされている。
狗奴国と邪馬台国は戦い続けたが、3世紀から4世紀に東海から東北で古墳か前方後方墳から前方後円墳に移行しており邪馬台国が狗奴国を支配していったと推定される。
第6章 「空白の4世紀」に何が起きたのか?
3世紀には卑弥呼・壱与が女王になった事、5世紀には5人の倭王が中国の記録に残っている。また、5世紀には世界最大の墓である仁徳天皇陵が作られた。4世紀には何があつたのか?これを2つの古墳から考察していく。
1. 富雄丸古墳 (4世紀後半)
奈良県奈良市郊外付近の丸型の古墳である。前方後円墳でない事が特徴である。内部から発見されたのは巨大な鉄剣と銅鏡と木棺である。鉄剣は全長254センチの蛇行剣であり古代アジアで最大である。把、鞘も特徴的であり鞘ごと立てる為の石突もあり戦う為の武器ではなく装飾の意味が強い。また、銅鏡は盾の形をしており大きさは縦64センチ、幅31センチ、厚み5ミリと大きい。銅鏡の背面には想像上の生き物や緻密な文様が線状半肉堀りになっており倭国の独自の技術で構成されている。木棺は3つの部屋から構成され頭側の副室が1.3メートル、中心の埋葬する主室は2.4メートル、足側の副室は1.3メートルの大きなサイズである。主室には頭の部分付近には水銀朱の成分が検出された。主室の足側には竪櫛、足側の副室には3枚の銅鏡が発見された。竪櫛の存在から女性の可能性が出ている。木棺は日本固有の針葉樹1本を半分にして中をくり抜き、仕切り板を挿入し、残りの丸太の半分を合わせて中空を形成した構造となっている。これらの内容からかなりの身分の墓であるが、誰の墓であるかは不明である。
2. 櫻井茶臼山古墳 (3世紀後半)
ここでの特徴は発見された銅鏡の数と種類である。数は103枚であり、これまで発見された30数枚に比べて極めて多い。種類は中国で作られたタイプと卑弥呼が魏志倭人伝で魏から与えられたと言われるタイプと日本独自製造の3つのタイプに分類できる。
3.この時代の技術開発
中国から技術が輸入された金属加工や古墳の製造の土木技術が徐々に日本に浸透して日本での独自技術が進展していった時代が「空白の4世紀」とも言える。
第7章 ヤマト政権と朝鮮半島情勢
1. 当時の東アジア情勢
中国では3世紀から6世紀まで統一的政権が成立せず周辺国への影響が低下していた。朝鮮半島では高句麗が中国の東北地方から発祥し朝鮮半島に勢力を伸ばした。朝鮮半島では馬韓・辰韓・弁韓が小国家の連合体として存在した。
(年表)
BC100頃、高句麗 中国遼寧省付近にて成立、後漢に朝貢〜後漢に抵抗
220年 後漢王朝崩壊〜.三国時代
※ 高句麗 魏にも抵抗
280年 晋 中国を統一
313年 高句麗が楽浪郡を滅亡する ※高句麗の勢力が朝鮮半島に拡大
345年 馬韓が百済へ発展 拠点はソウル南部
356年 辰韓が新羅に東南部にて発展、南部の弁韓では加耶が連合体を成立
369年 百済が倭王に七支刀を贈る
369年 高句麗が百済来襲・百済が撃退
371年 高句麗が再度、百済来襲・百済が撃退
391年 倭国が侵略し百済と新羅を支配した
391年 高句麗 広開土王即位、高句麗独自の年号採用
396年 高句麗広開土王 百済攻略着手
399年 高句麗広開土王へ新羅から倭人侵略の苦情あり
400年 高句麗広開土王は5万の兵を用い倭人を大敗させた
404年 高句麗広開土王が、帯方郡に侵入した倭人を撃退した
412年 高句麗広開土王死去
414年 広開土王碑建立
420年 宋成立 ※晋崩壊
439年 北魏成立
527年 磐井の乱 ※倭国の国内の反乱
589年 隋が中国を統一
660年 百済滅亡 ※新羅の拡張
668年 高句麗滅亡 ※新羅の拡張
663年 白村江の戦い ※唐と新羅の連合軍に日本敗れる
2. 朝鮮半島での前方後円墳
朝鮮半島の南西部に日本の前方後円墳とほぼ、同じ古墳が複数発見された。日本では3世紀頃から前方後円墳は作られており、朝鮮半島での古墳は5世紀から6世紀であり前方後円墳は日本が発祥で朝鮮半島の南西部に拡張したと思われる。
第8章 倭の五王と激動の東アジア
5世紀に倭王として中国へ五回朝貢をしている。
413年 東晋に朝貢
421年 宋に朝貢 倭王・讃
438年 宋に朝貢 倭王・珍
443年 宋に朝貢 倭王・済
462年 宋に朝貢 倭王・興 ※安東将軍倭国王の称号
(475年 高句麗が百済の都を落とす)
478年 宋に朝貢 倭王・武
何故、倭王が宋に五回朝貢をしたのかは、高句麗との戦いである。この朝貢での倭の狙いは3つである。
1.朝鮮半島南部での軍事権
2.宋の東側を安定させる将軍の役割の獲得(安東将軍)
3.倭国王として認められる事
また、中国としては、増大する高句麗を抑える為にもパワーバランスを整える為に高句麗・百済・倭に情勢に合わせて称号を与えた。
この様な背景の中で475年に高句麗は百済の都の漢城(ソウル)を落とすが、それ以上南部には攻めていない。朝鮮半島南部の軍事権は倭国が握っていて倭が百済を支援する警戒があった為であった。宗も高句麗が強大になる事を抑制する狙いがあったと思われる。高句麗は騎馬部隊を有し、当時日本には馬はなく戦略上、騎馬の戦闘能力は大きな武器であり日本にとって高句麗は大変な脅威であったと考えられる。後々のモンゴルが世界を席巻した様に騎馬部隊は極めて高い戦闘能力を有し他国の脅威であったと推定する。
倭の五王は日本の天皇の誰に相当するのかは、確実でない部分はあるが、以下の通りである。
讃: 応神天皇、仁徳天皇、履中天皇の誰か
珍: 仁徳天皇、反省天皇のどちらか
済: 允恭天皇
武: 雄略天皇
興: 安康天皇
第9章 「日本」はいかに誕生したか?
弥生、古墳時代の画期的技術革新アイテムは馬である。馬は元々日本国内にはなく、大陸から持ち込まれた。馬は移動の効率を圧倒的に変革した。この新規技術は軍事面だけてなく農耕での生産量向上、情報伝達に大きく変革をもたらした。馬の関連内容として、飼育方法、甲冑等の金属加工技術にも大きな変革をもたらした。飼育に関しては、関東で飼育した馬を近畿に献上する事も確認された。また、甲冑では鉄の加工技術の量産展開が見られ武具として金型の存在も認められた。ヤマト政権は馬や鉄の加工技術を周辺国に展開する事で支配力を強めた。新規技術は近畿に留め軍事面での優位性を確保した。527年、古墳時代最大の内戦と言われる「磐井の乱」が勃発した。この戦いの背景は近畿だけでなく九州や関東にまでのヤマト政権の浸透があり、朝鮮半島との交易を独自に進める磐井に対してヤマトの大将軍である物部の麤鹿火が派遣され激しい戦闘があった。
これらの時代を経て古墳は作られなくなった。古墳の役割が終焉したと思われる。また、日本が倭から日本になり始めた時期であり、唐と新羅の連合軍に日本と百済連合軍が敗れる時期と重なる事が考えられる。

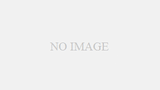
コメント